目次
ミスノートが「潜在意識」を「顕在意識」に変える― 成績アップの“最強の自己分析ツール”とは ―
実際に、ある中学生がこう話してくれました。
「最近ミスノートを作るようになってから、ミスが減りました!」
ミスノートとは、間違えた問題をまとめるノートです。
そしてこの子の言葉の裏には、非常に大切な意味があります。
つまり、この子は同じようなミスをこれまで何度も繰り返していたのです。それが、ノートに書くことで自分のミスを「潜在意識の中」から「目に見える形」に引き上げることができた。
これこそが、ミスノートの真の力です。
人は「気をつけよう」と思っても、意識できないものは修正できません。しかし、「あ、また同じ間違いをしている」と自分で気づけるようになると、脳はその行動を修正しようとします。
ミスを顕在化することで、ミスは減る。
ミスノートは潜在意識の中にあるミスを顕在化してくれる重要なツールなのです。
ミスノートは「間違いノート」だけではない
多くの子どもが、「ミスノート=間違えた問題を書き写すノート」と思っています。
でもそれでは、単なる「作業」に終わってしまう可能性もあります。大事なのは、なぜそのミスが起きたのかを考えること。
そのために、ミスを書くときには必ず
「これは知識のミスなのか? 行動のミスなのか?」
という分類を最初にすると効果的です。
知識ミス:知らなかった、忘れていた、勘違いしていた
行動ミス:問題の読み間違い、設問の見落とし、確認不足、時間配分のミス
たとえば、最近こんな質問を受けました。
「先生、この問題、なんでAじゃダメなんですか?」
私は問題を見て、すぐに気づきました。その設問には「B~Eの中から選びなさい」と書いてあったのです。Aは選択肢に入っていなかったのです。ちなみにAが選択肢に入っていたら、この問題の正解はAでした。
知識はちゃんと身に付いていたのに問題の条件を読んでいなかった。これは知識ではなく「行動のミス」です。ミスノートには、こうした「読み間違い」や「確認不足」もしっかり記録しておくことが大切です。
「行動ミス」は気づかないと直りません。
でも、ノートに書き出せば、その瞬間に意識が変わります。「自分はこういうときに読み飛ばす癖がある」とわかる。それだけで、次のテストでは同じミスを防げるのです。
ミスノートの作り方3ステップ
ONE進学塾では、特に具体的なノート作りの指導はしていません。各自がそれぞれ自分にとってわかりやすいノートを作ればいい、と思っています。
ただ、「どんなふうにノートを作っていいか分からない」という方に、ちょっとだけノート作りのヒントを差し上げましょう。3ステップで作ればいいと思います。
ステップ1:どんなミスをしたのか(問題内容)
ここは、間違えた問題の設問をそのまま書けば大丈夫です。
ステップ2:なぜ間違えたのか(原因分析)
まず最初に、「知識ミス」なのか「行動ミス」なのかを考えます。「知識ミス」なら、その知識のまとめを書きましょう。「行動ミス」なら、どんな行動をしてミスしたのかを書きましょう。「知識ミス」「行動ミス」で色分けしてみても良いでしょう。知識→赤 行動→緑 など。
(知識ミスの例)
・力学的エネルギーについて
頂点:位置エネルギーMax、運動エネルギー0
地面:位置エネルギー0、運動エネルギーMax
・古代の土地制度 順番間違えない
班田収授法(645~701)→三世一身の法(723)→墾田永年私財法(743)
(行動ミスの例)
・設問中の「B~E」を「A~E」と読み間違えた。
・「適切でないものを選びなさい」なのに適切なものを選んだ。
・「当てはまる記号すべて書きなさい」なのに1つしか選ばなかった。
ステップ3:次はどうするか(改善策)
どうすればこのミスが減るか、今後の行動指針を書きましょう。
(例)「力学的エネルギー」のテキストを3回解く
(例)「奈良時代」のテキストを覚えるまで反復
(例)設問中に書いてある選択肢に〇を付ける
ですからノートは3分割します。
ノートに縦線を2本引き、左は2/5スペース、中央も2/5スペース、改善策を書く右は少し少な目で1/5スペースの3分割です。
あくまでこれは私の示す一例です。みなさんは好きなようにミスノートを作ってみてください。作り方より、ミスノートを作るという行動に即移すことが何より大切です。どんなのを作っていいかわからずに行動がとれないという方に、私の例が参考になればと思い、書きました。
「うちの子、同じミスばかり・・・」と思ったら
それは「努力不足」ではないかもしれません。
「記録不足」の可能性が大きいかもしれません。
多くの子は、ミスノートの記録をしたがりません。それは当然です、誰だって自分のミスと向き合いたくありませんから。ミスを直視するのは大人でも辛いです。しかし、直視しないとそのミスはずっと治らないのもまた事実です(「直らない」ではなく、あえて「治らない」としました)。
ミスをノートに書くというのは、自分の行動を観察し、修正する練習。
これを繰り返す子は、間違いなく強くなります。
自分のミスを直視できる子は、絶対に強いです。
ミスを減らすために必要なのは「才能」ではなく「仕組み」。
そしてその仕組みこそが、ミスノートです。
ミスから学べることは多くある
私がミスノートを推奨しているのは、間違いを責めるためではありません。「失敗の中にこそ、成功の種がある」ことを実感してほしいからです。これは勉強に限ったお話ではなく、人生においてもです。
最初から完璧な人はいません。
大切なのは、失敗を「放置」か「活かす」か。
ミスノートは、失敗を「活かす」最高のツールです。
今日のミスを、明日の成長につなげる。
その繰り返しが、合格を掴む力になります。
そしてその力は、受験勉強を通じて得られる「一生使える力」になります。
受験勉強を通じてお子さんの人生を少しでもハッピーにできたらな、と思います。
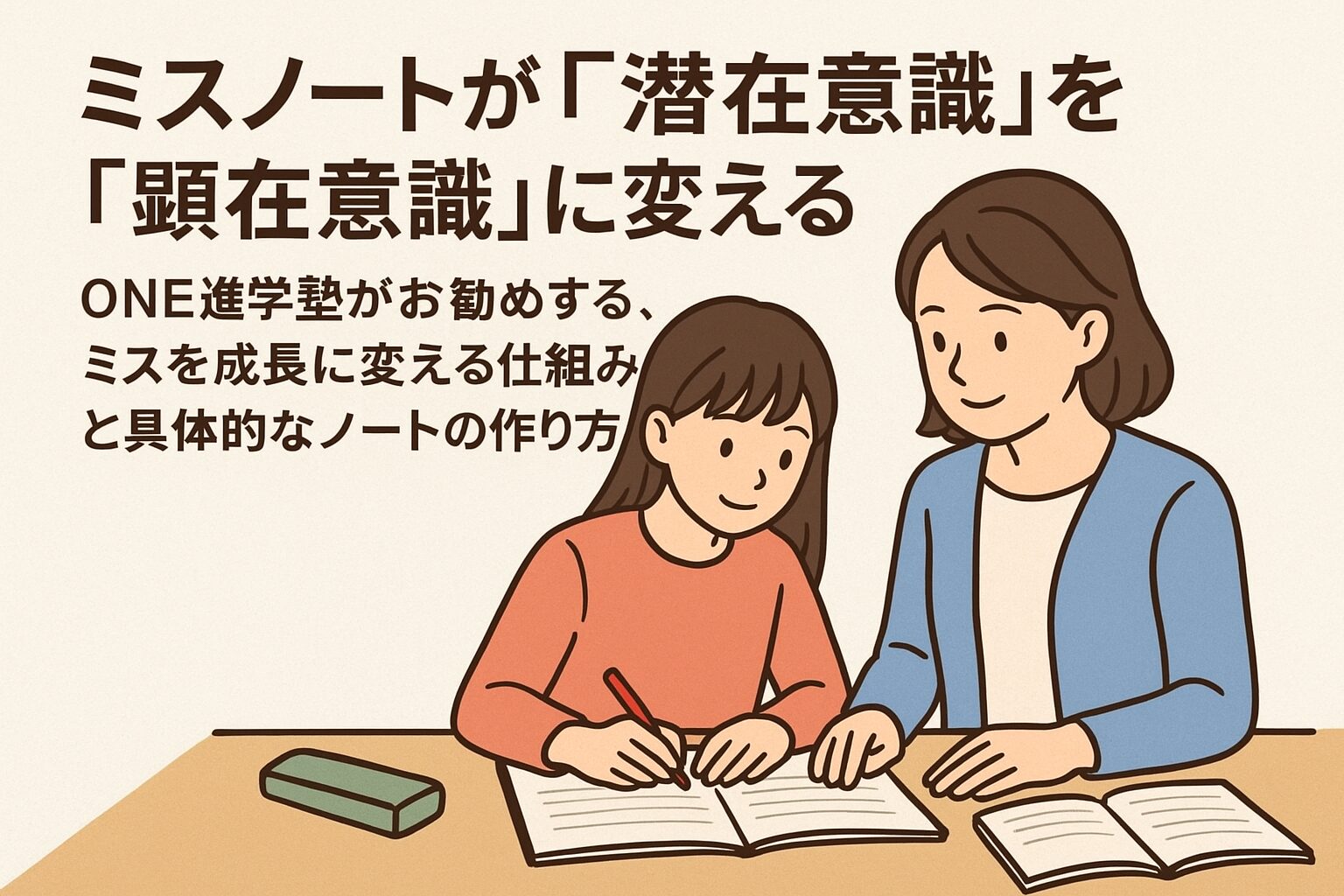
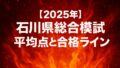

コメント