いよいよ明日18日(月)の朝10時から、夏期講習の後半戦がスタートします。
「よし、明日は10時に教室に行って、すぐに勉強開始だ!」
と気合いを入れてくれるご家庭もあれば、
「後半戦が始まったばかりだし、少しのんびりスタートで大丈夫かな」
と思われる方もいるかもしれません。
どちらも自然な反応ですが、
あえてここで率直にお伝えしたいことがあります。
早く動く子は、やっぱり伸びやすい。
これは塾で30年以上子どもたちを見てきて、確信していることです。
「早く動く」ことの大きな力
勉強において
「早く始める」「早く取り組む」という姿勢は、
それだけでお子さんを有利にします。
小学生から塾に通わせることに対して、
「まだ小さいのに勉強漬けはかわいそう」
と感じられる保護者の方もいらっしゃいます。
確かにそのお気持ちは理解できます。
ですが、やはり早くから学習習慣を持った子は、結果的に学力がぐんぐん伸びやすいのです。
なぜなら、
「勉強はやるものだ」という意識が
幼いころから当たり前になるからです。
遊びや習い事と同じように、
日常の一部として学びを取り入れることができる。
その積み重ねが、数年後に大きな差となって表れます。
習い事が多すぎると、迷子になってしまう
ただし、早く始めることと同時に大切なのは「選び方」です。
よく「船頭多くして船山に上る」ということわざが使われますが、
学習にも同じことが言えます。
塾をいくつも掛け持ちする「兼塾」や、
塾系の習い事を3つも4つも重ねると、
かえって子どもが迷子になってしまうケースが多いのです。
例えば、私自身の国語指導は
「答えを見つける技術」に特化しています。
しっかりとした読解力がなくても、
テストで点を取るための答案をつくる。
文学や表現の深い理解には向きませんが、受験という場面では効果を発揮します。
※私の国語指導は、大学受験の共通テストくらいであれば通用しますが、東大文系の2次試験だと通用しません。ただ、中学高校受験であれば、桜蔭中学以外なら多分通用します。桜蔭の国語は、おそらく日本一難しい。
一方で、真っすぐに読解力を鍛える指導
をする先生もいらっしゃいます。
どちらが良い悪いではありません。
ですが、両方を同時に学ぶと、
子どもは「どっちを信じればいいの?」と混乱してしまうのです。
これは国語に限らず、英語や数学でも同じです。
指導方針がぶつかる環境を作ってしまうと、
せっかくの努力が実りにくくなってしまいます。
伸びにくい子の共通点
長年の経験から見えてきた「伸びにくい子の特徴」をあえて2つ挙げるなら、
行動が遅いこと
塾系の習い事を3〜4つ以上抱えていること
この2点です。
逆に言えば、
行動が早く、習い事を絞ってバランスをとっている子は、
驚くほど成長していきます。
例えば、今ぐんぐん伸びている中学生がいます。
小学生のころは
「御成敗式目」を「ごせえばいしきもく」と書いてしまうくらいの子でした。
でも、今では数学・理科・社会で90点以上、
時には満点に近い点数を取るまでになっています。
勉強自体は決して好きではないようですが、
行動はいつも早い。
そして習い事もきちんと取捨選択ができている。
その姿勢が、結果として大きな成長につながっているのです。
「今」から動くことが、未来の自信につながる
保護者の皆さまにぜひお伝えしたいのは、
受験に向かう道は「早めに動くほど楽になる」
ということです。
夏期講習の後半戦が始まる今こそ、
良いスタートを切る絶好のタイミングです。
今日一日をどう過ごすか、明日の10時をどう迎えるか。
その一歩の違いが、数か月後、数年後のお子さんの姿を大きく変えていきます。
もちろん、無理をして詰め込みすぎる必要はありません。
大切なのは「一歩を早く踏み出すこと」と「習い事や学習の環境を整理してあげること」。
それだけで、お子さんは驚くほど伸びやすくなります。
最後に ― 私からのメッセージ
私はこれまで6000人以上もの子どもたちと向き合ってきました。
その中で強く感じるのは、
子どもたちは誰一人として「勉強ができないまま終わる子」ではない、
ということです。
早いタイミングで、正しい環境を整えてあげれば、どんな子も必ず伸びていきます。
ですからどうか、保護者の方も安心してください。
そして明日からの夏期講習後半戦、お子さんが
「よし、やるぞ!」と元気に一歩を踏み出せるよう、
ぜひ背中を押してあげてください。
私も全力でサポートします。
明日、教室でお子さんの笑顔と真剣な表情に会えるのを、心から楽しみにしています。

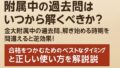
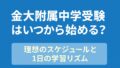
コメント