金大附属中学受験の国語で問われる力とは?
金沢大学附属中学の入試国語では、
ただ文章を読むだけでは太刀打ちできません。
必要なのは「読解力」に加え、
「要約力」「記述力」そして
「抽象的な内容を自分なりに解釈し、考える力」です。
過去5年の出題傾向を見ると、
物語文よりも説明的文章の難易度が高く、
その中には哲学や環境、宗教、行動科学といった
小学生にとってはあまりなじみのない分野
も登場しています。
つまり、金大附属中学の国語では、
「初めて読む、ちょっと難しめな説明文」
をどれだけ理解し、自分の言葉でまとめ、
意見を述べられるかが問われているのです。
「うちの子は読書が好きだから国語は大丈夫」
と思っていても、読んでいるのが物語ばかりでは
金大附属中学の入試問題に対応するには不十分。
読むべきは、抽象的で論理的な文章なのです。
そこで、私たちONE進学塾では、
このような国語力を段階的に育てるため
の取り組みを始めました。それが——
説明的文章を読む力をどう育てるか
「金沢大学附属中学受験 読書の会(仮)」は、
土曜日を中心に実施している読書・要約の学習会です。
この会では、
金大附属中学入試において過去に出題された本や、
出題傾向に沿った説明的文章を集め、
生徒たちに読ませています。
読ませるだけではありません。必ずそのあとに、
・要約文の作成
・感想の記述
・疑問点や学びの整理
などを行います。
特に要約の練習は、
子どもたちにとって簡単なものではありません。
最初は「あらすじを書けばいいの?」と戸惑いますが、
訓練を重ねることで、
文章の核となる部分を的確に抜き出し、
100字~200字程度でまとめられるようになってきます。
このプロセスを通じて、子どもたちは、
・文章を構造的に捉える力
・重要な情報を取捨選択する力
・要点を短くわかりやすく表現する力
を少しずつ身につけていきます。
これらはまさに、金沢大学附属中学の国語入試が求めている力そのものなのです。
書く経験が減っている子どもたちに必要なこと
近年、子どもたちの「書く力」が著しく低下しています。
理由はシンプルです——書く機会が圧倒的に減っているからです。
たとえば学校の授業では、
黒板を写すのではなく、
先生が用意したプリントの穴埋めをするだけで済んでしまう。
メモも、スマホで写真を撮れば完了。
日記や感想文なども、家庭でわざわざ紙に書くことは少なくなっています。
その結果、文章を書くときの基本が身についていない子が増えています。
・文末が敬体(です・ます)と常体(だ・である)でバラバラ
・無理やり体言止めを使ってみたり、倒置法や比喩表現を間違って使っていたり
このような文章を書いてくるのにもかかわらず、
模試では90点以上を取ってくる子もいます。
なぜなら、選択肢を選ぶ読解力と記述力は別物だからです。
記述で差がつくのは、まさにこうした
「書き慣れているかどうか」です。
金沢大学附属中学の入試には、
国語だけでなく、
理科・社会を合わせた「総合」でも記述問題が出題されます。
内容を読み取り、自分の言葉で説明する力
が、合否を左右するのです。
「読書の会」で育てる国語力と学力の土台
ONE進学塾の「読書の会(仮)」には、
4つの明確な目的があります。
1.金沢大学附属中学の入試に必要な国語力を知る
過去に出題された本を読み込むことで、求められているレベルを実感します。
2.説明的文章に触れる機会を増やす
日常生活ではあまり読まない、抽象的なジャンルにあえて触れさせます。
3.書く力を実践的に伸ばす
要約や感想文の訓練を通じて、文章構成力を自然に育てていきます。
4.新しい視点・世界観を獲得する
読書を通じて「考えるきっかけ」を得ることができます。
この活動の一番の特長は、
書いた文章を塾長がすべて直接添削していることです。
アルバイト講師に任せるのではなく、
子ども一人ひとりの表現と向き合い、
丁寧にフィードバックを行います。
おわりに
金沢大学附属中学受験を目指すのであれば、
単なるテスト対策ではなく、
思考力・表現力を育てる取り組みが必要です。
「読書の会」はそのための一つの方法です。
これからも、より多くの良書を教室に揃え、
子どもたちと一緒に読み、考え、書く時間を作っていきます。
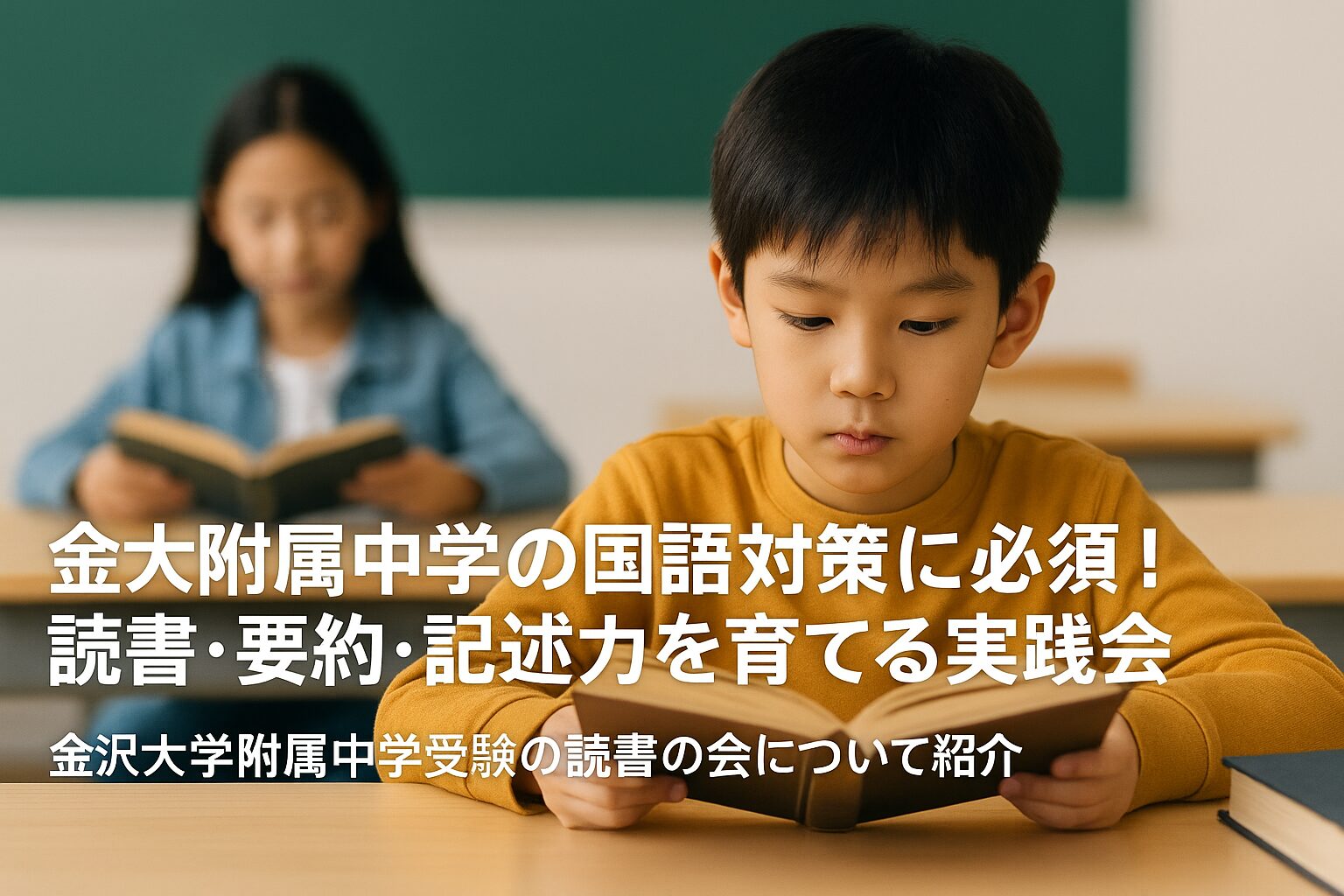


コメント